海田町の稲荷町にたたずむ明顕寺(みょうけんじ)は、1541年に開かれた長い歴史を持つ寺院です。立派な山門や重厚な本堂が印象的で、地域に根ざしたお寺として、地元の人々に親しまれています。この記事では、明顕寺の基本情報や歴史背景、現地の様子をまとめました。
基本情報
- 住所:広島県安芸郡海田町稲荷町1−2
- 宗派:浄土真宗本願寺派
- 駐車場:記載なし
- 拝観時間:記載なし
歴史や背景
明顕寺は天文10(1541)年に創建され、浄土真宗本願寺派に属しています。現在の立派な山門や本堂は歴史的価値が高く、特に総高127cm、口径70cmの梵鐘は江戸時代初期の鋳物技術を示す文化財です。
この梵鐘は、海田市の三商人によって寄進され、宝暦2年(1752)に再鋳されたもの。鋳物師は芸州鋳物師筆頭総代として知られた名工・植木(金屋)源兵衛と新兵衛でした。
また、慶応元年(1865)には越後高田藩主・榊原政敬の軍が海田に宿陣し、翌年の戦で亡くなった藩士34名が境内に葬られています。
さらに、1945年8月6日の原爆投下後には、明顕寺が避難者の収容所として使用された記録が「広島原爆戦災誌」にも残されています。
現地レビュー
(仮:未訪問/訪問後追記と記載)
まとめ
明顕寺は戦国期から続く長い歴史を持ち、鋳造梵鐘や越後高田藩士の墓、さらには原爆避難所としての記録など、さまざまな時代の記憶を今に伝えています。古き良き海田の歴史を体感できるこのお寺は、地域史に興味がある方にとっても訪れる価値のある場所です。

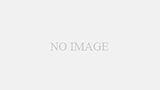
コメント